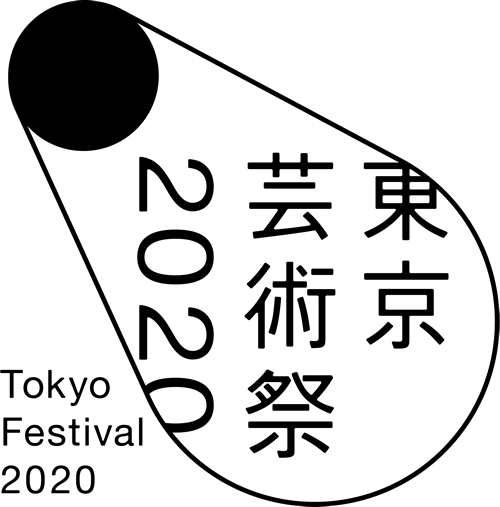東京芸術祭ワールドコンペティション2019観客賞受賞
ボノボ『汝、愛せよ』公演関連オンラインレクチャー
『南米チリの諸相と演劇の変遷』レポート
10月30日(金)、<東京芸術祭ワールドコンペティション2019観客賞受賞>ボノボ『汝、愛せよ』の公演関連オンラインレクチャー『南米チリの諸相と演劇の変遷』が開催された。講師は仮屋浩子先生(明治大学教員)。スペイン文学、スペイン語圏、カタルーニャ語圏演劇の研究者であり、「Raíces Teatro」主宰として、在日スペイン語話者のアーティストとの作品づくりやスペイン語圏劇作家とのコラボレーション、作品の翻訳を手がけている。
レクチャーでは、約1時間半にわたって、チリの地勢や歴史と、作品紹介を含む演劇の変遷、文化状況までが俯瞰的にかつ深く語られ、充実した時間となった。
レクチャーでは、約1時間半にわたって、チリの地勢や歴史と、作品紹介を含む演劇の変遷、文化状況までが俯瞰的にかつ深く語られ、充実した時間となった。

講師の仮屋浩子先生
続いて、“チリの地理”。ダジャレではないですよ、と先生。南米の南太平洋側に位置し、唐辛子のような細長い形状をしており、全長は4270㎞。面積は日本の約2倍だが、人口は2000万人弱と少ない。ペルー、ボリビア、アルゼンチンに隣接し、首都はサンティアゴで、総人口の3分の1が集まっている。
ここでまた参加者に向けて、『汝、愛せよ』は、誰が言った言葉でしょうか?との質問が。

答えはイエス・キリスト。スペインの植民地時代に根をおろしたキリスト教は、チリの文化に多大な影響を与えている。
ここから、お話はチリの歴史へ移っていく。先生は時代を1536年までの「前スペイン時代」、1598年から1808年までの「植民地時代」、1818年以降の「独立後」、1973年から1990年の「軍事独裁政権」、1990年以降の「民政移管」に分け、大きな歴史の流れとともに、演劇の変遷を解説していく。
チリの先住民はマプチェ、アイマラ、ケチュア、アタカマといった族がありますが、その80%、チリ全体の人口の4%を占めるのがマプチェ族。『汝、愛せよ』の舞台美術では、マプチェ族の意匠が使われている。舞台のプロローグでは、先住民らしき人物とキリスト教の司祭らしき人物が登場し、ふたつの世界のはざまでの、現代にまで続く違和感が提示される。
植民地時代の演劇はスペイン人がもたらしたものであり、キリスト教の典礼と関係のある作品—イエスの誕生や受難劇、聖体神秘劇などが多くつくられた。イエズス会による、政治家や弁護士、司祭を目指すエリートを育成するため、修辞学(レトリック)を学ぶ一助として演劇が利用された。一方で大衆娯楽劇も上演され、主要都市で劇場が建設される。
独立し共和国となった後は、国民を教育するために演劇を政治的に利用する時代があった。その後、20世紀初頭にはチリ産の硝石ブームによって起こった経済発展にともなった社会問題や不安が浮上する。演劇は、19世紀終わりから20世紀初頭にかけて、国のアイデンティティと深く結びついた国民演劇が登場。鉱山を擁するチリでは、その働く現場から労働者演劇、民衆演劇も数多く誕生する。さらに、その後、大学演劇が台頭。思想的で政治色の強いものが出てくる。
20世紀後半、サルバドール・アジェンデが政権を握り、世界で初めて選挙による社会主義政権が誕生するが、ハイパーインフレを招き、混乱に陥る。1973年9月11日、第二のキューバとなることを恐れたアメリカ政府およびアメリカ多国籍企業主導で軍事クーデターが勃発。911というとアメリカ同時多発テロを思い浮かべる人も多いと思われるが、チリの「911」はこのクーデターの日として記憶されている。ピノチェトが大統領に就任し、以降、政治批判をする人に対して人権抑圧が当たり前になっていく。演劇人も打撃を受け、メンバーの逮捕や亡命が相次ぐ。一方、娯楽としての演劇は民衆にとって必要なものとされ、内容の薄い作品の上演や、シェイクスピアなどの古典、商業演劇が幅を利かせるようになる。しかし、抵抗運動としての演劇は存在し続ける。ブラックユーモアを使って社会問題を扱うなど、検閲、監視という制限された中で芸術家たちは独自の表現を追求することになる。また、住民たちに直接届く路上演劇も生まれる。さらに1980年代になると、集団創作が盛り上がりを見せるようになった。この時代に重要な人物としては、演出家・シンガーソングライターのビクトル・ハラと、パッチワークを表現の手段にした女性たちのグループ、アルピジェラスが紹介された。
90年代に入り、周辺国が民主化の道をたどる中、ピノチェト軍事独裁政権崩壊。しかし、ラテンアメリカのいわゆる優等生として“アメリカの裏庭”として新自由主義の実験場とされてきたチリの経済状況はさほど変化することはなかった。
昨年から今年にかけて、地下鉄の運賃値上げをきっかけとしてチリで大規模なゼネストが起こり、軍と労働者民衆が衝突。今年の憲法改正の国民投票へと大きなうねりを見せている。
演劇の傾向は、リアリズム、セリフ中心の伝統主義派に対して、革新主義派が台頭。民政移管となっても大きな声でものが言えない状況を打破するべく、言葉(テクスト)よりも、よりビジュアルやフィジカルなものに重きが置かれた。また、テクノロジーを生かした演出なども生まれる。代表的なグループとしてラ・トロッパ、演出家としてラモン・グリフェロ、マウリシオ・セロドン等が動画を交えて紹介された。マウリッシオ・セロドンは「テアトロ・デル・シレンシオ(沈黙の劇団)」を主宰。パントマイムとモダンダンスを融合させたような表現や、ライブ演奏、劇場ではなくオルタナティブな場所での上演を行っている。
民主化した初期の段階では、一体何が起きていたのかを直視できない、歴史的解釈の不可視化ともいうべき民俗的傾向の強い作品が多かったが、次第に、独裁体制や人権侵害にスポットを当てたものが出てくる。また、女性やLGBT、ホームレスといった周縁の存在からの視点、家族や暴力の問題に焦点を当てたものがテーマとして浮上している。この中で、1980年生まれのマヌエラ・インファンテにスポットを当てた。演劇は哲学的エッセイであり、建築物と考える彼女は、フェミニズム演劇は、それまでの人間(男性優位、家父長制、資本主義)中心ではない演劇を目指すものであるとする。
『植物国家・状態』(2017)という作品では、枝分かれというような植物の特性を作品の構成に入れ込んだり、たとえば太陽が東からのぼり西に沈むといった照明の効果を使うというように、植物を主体として描き出し、人間中心の世界へ一石を投じている。
現在、サンティアゴでは小劇場、独立劇場が24あり、地域に文化センターがあり、社会事業として演劇の上演を行っている。また、演劇祭の実施や、国外への演劇祭への積極的な参加などで、国際化が進んでいる。演劇はチリの人にとっては日本より身近にあるのではないか、と先生。5月11日は演劇の日として制定されているという。 レクチャーの終盤、劇団ボノボについて詳しく説明されたのち、チリの文化人の解説と、映画監督や作品が語られた。
質問では、チリの演劇教育に関することなどが寄せられた。そして「チリの演劇の魅力は?」の問いに先生は、「ただの娯楽ではない、社会とつながっていること」を挙げた。正面から社会問題を扱うものもあるが、おもしろおかしく描いているもの、美しく描くものなど、ジャンルは多彩だ。
チリの歴史と演劇の変遷を見て気がついたことがある。それは社会情勢が不安な中にあっても、決して演劇はなくならず、生き続けているということ、そして社会の状況に応じて、表現は絶えず変化しているということである。
コロナ禍を経て、次の時代のチリ演劇がどこへ向かうのか。関心を寄せていきたいと感じたレクチャーだった。
文:土屋典子(ライター)