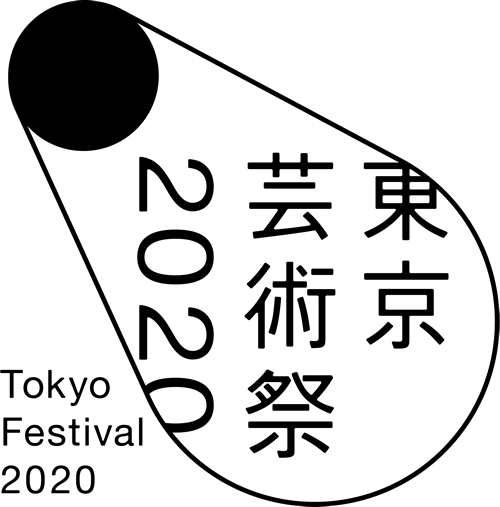『ビッグ・ナッシング』観劇レポート
影絵をどのように投影しているのか序盤映像では分からなかった。戴陳連自身が影絵の中に入る部分でも影絵は動いていたが、あれは事前に収録されているものなのだろうか。後半は明らかに戴陳連が影絵を動かす様子が見て取れた。何につけても今回は、序盤は特に、戴陳連が舞台上で行っていることがどのように影絵に作用しているのかが全く分からなかった。直接パフォーマンスを見ることができなかったのが何より悔やまれる。
内容の話に戻る。いろいろなシーンが断片的に記憶に残っている。しかしそれはぼんやりではなくかなり強烈に。ひとつは舟をこいでいるシーン。私は藤城清治の影絵が好きで、よく美術館に足を運ぶのだが、舟をこぐという行為を、普通に横からとらえた後に、水面下から見たような形での表現したことに思わず膝を打った。影絵は二次元の表現の中でも特にその要素が強いように感じていたが、そのシーンを見たときにぐっと三次元に世界が広がったような感覚を覚えた。
もうひとつ印象的なシーンはやはり、人の腕から口が生え、それが様々な食材をむさぼるシーンだ。とても強烈で、それでいて滑稽で、なんとなくかわいらしくもあり恐ろしくもあった。それとともに不思議な安心感もあった。なぜかこの場面はずっと見ていられると思った。またこのシーンに出てくる食材の影絵がとても具体的で何を表しているのかすぐにわかった。そのため、次は何の食材だろうという単純なわくわく感が自分を支配したのを覚えている。夢を純粋に楽しむ子供のような気持だったのかもしれない。そんな場面の後、後半にかけて、すさまじい場面が続く。骸骨が出てきたり、大量の虫が出てきたり、戴陳連がスプレーのようなものを何かに吹きかけ、すさまじい音を鳴らしたり。私の頭に浮かんだイメージは「公害」や「害虫」「汚染」などでであった。虫が大量に出てきて、スプレーがまかれ、植物が枯れ果てたように感じた。街が退廃しすべてが失われたような感じがした。そして静かにたたずむ停車場のようなもの。そこに人が来て、馬が来て。人が塔になってしまう。正直理解できなかった。ただ静けさだけが私を包んでいるように感じた。嵐の去った後のような、すがすがしいと言っていいのかわからないが、どこか晴れ晴れとした、絶望的な状況と共に希望のようなものが見えた。
ここまで内容について書いてきたが、この作品を見ている途中までは、戴陳連の意図を必死にくみ取ろうとしていた。だが途中でそのことをやめてみた。そしてその一つ一つのシーンに対して抱いたものを純粋に記述してみた。もしかしたらいや、確実に戴陳連の描いたものとは乖離しているだろう。しかしこの「ビッグ・ナッシング」という作品名に「自由でいい」と言われているような気がした。