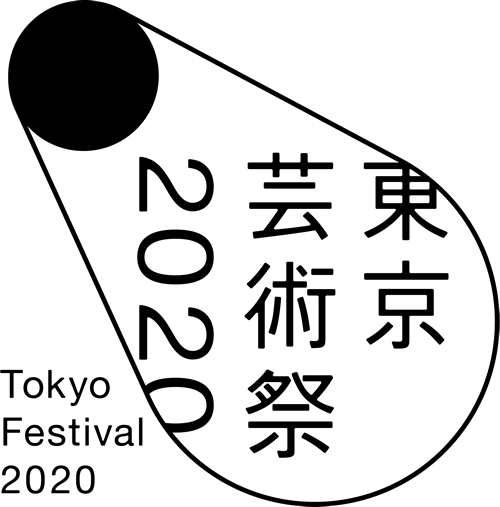『汝、愛せよ』観劇後座談会レポート

11月6日、『汝、愛せよ』観劇後座談会が東京芸術劇場ミーティングルーム3にて開催された。参加したのは日本大学芸術学部大学院で学ぶ明利翔さん、上原諒子さん、嶋孝脩さん、藤江露沙さん、徳永伸光さん、そして韓国からの留学生の崔圭桓さん、中国からの留学生の李韓篠さんの7名。司会進行は同大学の藤崎周平先生が務めた。
『汝、愛せよ』はチリの劇団ボノボによる作品だ。2019年度の東京芸術祭ワールドコンペティションで観客賞、批評家賞、最優秀パフォーマー賞の3つの賞を受賞した。日本からすると地球の裏側にあたる遠い国の作品だが、学生たちは作品からの問いかけをそれぞれの立場から「我がこと」に引き寄せ、多彩な視点からの感想を語り合った。
『汝、愛せよ』はチリの劇団ボノボによる作品だ。2019年度の東京芸術祭ワールドコンペティションで観客賞、批評家賞、最優秀パフォーマー賞の3つの賞を受賞した。日本からすると地球の裏側にあたる遠い国の作品だが、学生たちは作品からの問いかけをそれぞれの立場から「我がこと」に引き寄せ、多彩な視点からの感想を語り合った。
作品の感想を「一言」で表すと?
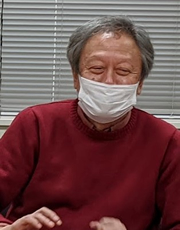
藤崎周平先生
李「責任感」
崔「差別」
明利「孫の手」…です。
徳永「動物」
嶋「アイロニー」
上原「空気」
藤江「気まずい」
──まず、わかりやすいところから崔君の「差別」から始めましょうか。韓国ではこの問題はどう扱われていますか?
崔韓国はずっと単一民族の国という認識でしたが、今はそうではなくて、多民族の国だという認識になっています。また、これまでは韓国人が海外で差別されること、「私たちは被害者である」という問題意識で語られることが多かったですが、今は「私たちも加害者になり得る」という問題意識も出てきました。
──中国はどう? 李君はとくに、少数民族の多い雲南省の出身なので、今日のメンバーの中でもこの問題は一番身近ではないかと思うのですが。
李差別は生活の中どこにでも存在していますし。日本でも感じることがあります。つい先日も部屋を探したとき、とても良い部屋が見つかったのに「外国人はダメ」だと断られてしまいました。

徳永伸光さん
徳永僕は子どもの頃太っていて、よく言われたので…この作品を見たときも「そういうことってあるよね」と思ったんです。でも、それが愛情表現の場合もあるし、見極めが難しい。
嶋飼い犬と野良犬、つまり予防接種をしている犬としていない犬の区別はしますよね。今後、コロナのワクチンができたとき、人間に対しても同じことをするのかな? 今の時代、それをリアルに感じます。
上原私は動物の名前が差別的に使われているということは、言われて初めて「ああ、そうだな」と気付きました。こちらにそういうつもりはなくても、相手にそう思われたらそれは差別だと思います。
──学校でも友だちにあだ名をつけたりするじゃない? ミュージカル『コーラスライン』にも出てくるけれど、うっかりおならをしてしまった人が「スカンク」と呼ばれるようになっちゃうとか。
明利僕は小さい頃、顔に対して鼻の穴が大きくて「マキバオー」と言われていた記憶があります。人間は動物のことを下に見ているのかもしれない。ペットという存在からしてそうですよね。
崔ペットのように人間が可愛がる動物もいるし、嫌う動物もいます。子どもの頃は相手の特徴をつかんで動物の名前で呼ぶのが面白いけれど、相手にとってはそれが忘れられないことになるかもしれない。それにしても、今日の舞台にも出てましたが、男が「ウサギ」と呼ばれて傷つくのは全世界同じなんですね。
藤江嶋君の飼い犬と野良犬の話はすごくよくわかります。昔から野良犬は狂犬病などバイ菌を持っていそうな感じがしてあまり触りたいとは思わなかった。私は中国人の親がいて、テレビなどで、よく「中国人は礼儀知らず」だと言われますが、それは日本人にそういう先入観があるからかもしれないと思います。中国人が全員礼儀知らずとはかぎりません。中国人は犬を食用にしますが、日本人はそう聞くと「かわいそう」だと言うんですよね。同じ動物である牛や豚は食べるのに。
「アイロニー」は芸術の武器、使う人には「責任感」が必要
──藤江さんは「気まずい」という言葉を挙げてくれましたが?
藤江劇の最初から何度も出てきたワードなので、きっと何か伝えたいことがあるのだと思ったのです。とくに最後の「気まずくなくなったら会議を始めよう」という台詞はいったいどういう意味なのかな?と、頭の中でぐるぐると考えていました。

崔圭桓さん
崔たとえば日本の人はどういうときに気まずいですか?
明利常に気まずいって感じ!
嶋「気まずさ」が原動力で会話が進む!
崔日本には「気」がつく言葉が多いですよね。
嶋それは気がつかなかった(笑)
──今はどんなに遠い国の芝居を見ても自分たちのことのように感じられるから、やはり世界はつながっていると実感できるよね。明利君の「孫の手」はどういう意味?
明利日本には「孫の手」という道具があるんですけど…背中がかゆいのになかなか手が届かない、でも、そこに手が届いた感じがしたので「孫の手」です。差別はあると知っていても実際に触れたことがなくて、でも、この作品を見てそこに手が届いた感じがしました。
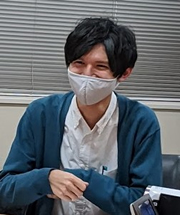
嶋孝脩さん
嶋冒頭で先住民族が登場した後に、アメナイトを差別する地球人を登場させるという見せ方、つまり人は差別の加害者にも被害者にもなり得るという、その両義性を見せつけられたとき「皮肉(アイロニー)」という言葉が思い浮かんだんです。
上原昔も今も、人はずっと同じことを繰り返しているのだと言われている気がしました。
藤江私は中国のインターナショナルスクールに通っていたんですけど、「アイロニー」「風刺」という言葉は教科書のあちこちに出てきて、あらゆる物語の中で何が風刺か、何がアイロニーかを学びます。それは日本との大きな違いですね。私も外見は日本人に見えるから、日本で当たり前のことを知らないと「バカなの?」という目で見られるように、「日本人に見えるか」あるいは「中国人に見えるか」で、途端に脳が違う働きをするのだといつも感じます。アメナイトを差別せずにはいられないという思考も脳の底にこびりついているものだということ、それがこの話の「皮肉」だと思います。
李芸術作品はアイロニーという力を使えるから、その力をどう使って伝えるかについての責任感を持たなくてはいけないと思います。
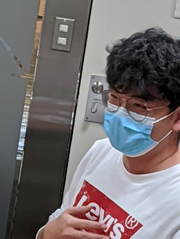
李韓篠さん
李芸術は創作物であり、自由な手段で様々な価値観や皆が知らないことを伝えられます。この劇からも、遠い国のことなのに色々と考えさせられました。伝える側の「責任感」を感じたのです。
──受け手の側の「責任感」も大事なのでは? これは国によって違っていて、日本ではこれまで演劇は娯楽であり、エンタメとして受け取られることが多かった。でも、この東京芸術祭のような場がマイノリティの個人や集団の作品を見せてくれることで、観客側もだんだん「責任感」を持っていけるのではないだろうか、これは大事なことかもしれない。この作品も、劇場を出た人に新たな視界を与えてくれて風景が変わって見える、そんな作品だったと思います。
「腹を割る」衝撃のラストシーンから何を受け取る?
──では、作品の中にもう少し入って、印象的だった部分についてさらに聞いていきましょう。
藤江差別に対してどう考えて、どういう行動をするか?について、すべてに責任があるなと、そして行動しないことに対しても責任は生まれるんだなと感じました。
上原強烈なシーンはいくつかありましたが、最後のシーンで女の人が先に手を出したのに、取り押さえられたのが男の人だったのは印象的でした。もう一つは、女の人のお腹の傷です。リアルに「腹を割る」だと思いました!
藤江英語だとcut yourselfと訳されていました。元のスペイン語がどうなのかが気になります。
嶋作り手も観る側も、それぞれ独自の文化コードを持っているわけで、どちらにも転べるし色んな味方ができる。それを一面的に受け取ってしまうのはもったいないと思います。でも「腹を割かれて痛い」ことは、世界中の誰もが何の揺らぎもなく共感できますよね。
徳永アルトゥールがタクシーの運転手を殺してしまった話から、アメリカで黒人が白人の警察官に殺された話を思い出しました。加害者である警察官にも思いを馳せないといけないのでは?と思うのです。

明利翔さん
明利僕も最後に切り裂かれたお腹を見せるところが一番印象的で、「愛するって何だろう?」とすごく考えさせられました。戦争だって最初は互いの正義から始まるわけだし、DVももしかして愛から始まるのかもしれない? 争いや暴力は「愛すること」と紙一重、だとしたら本当の愛とは何だろうと思いました。
──最後のシーンは舞台より映像の方がよりショッキングに感じられるかもしれません。私たちの未来を考えるための象徴的なシーンでした。
崔僕の語学力ではこの作品の全てを理解することが難しかったけれど…チリはスペインの植民地でしたが韓国も植民地時代があり、そうした国には不満を発散させるための悪口が多いという話を思い出しました。また、医者のように十分な教育を受けて知的レベルが高いはずの人たちが自由ではないのも皮肉だなと思いました。もしかしてエリート集団より、農業をしているような人の方が自由なのかもしれないです。
李僕は2つのことを思いました。一つは、エピソードの中も劇全体と似ている仕組みを使った、その方法がとてもうまいということ。もう一つは、スペイン語が耳から入ってきて、英語と日本語の字幕をそれぞれ読むことになって大変でしたが、日本語訳には何となく違和感があるということです。これは言語として英語の方がスペイン語に近いからでしょうか? スペイン語には「お腹」という言葉は出てこなかったです。
「息を吐かせてあげること」もアートの役割

藤江露沙さん
藤江英語が…びっくりするほど弱いなと思います。そして、もっと色んなものに触れられる環境を作ってあげるのが望ましいです。親が「これはダメ」と決めつけることが多いので、子どもの興味をもっと受け入れてあげられたらいいのにと思います。とくにその差を感じるのが芸術です。インターナショナルスクールは自由で、自分の表現したいことが尊重されたのに、日本はデッサンの正確性ばかり求められて、クリエイティビティは関係ない。思考が閉鎖的になっていくのを感じました。あとは、日本の大学にもっと演劇系の学部学科が増えたらいいなと思います。
──引き続き考えていきましょう。
嶋演劇は「同化」も「異化」も両方できる、その立体感を提供できるのが演劇だと思います。これはバイト先で聞いた話なのですが、ある人がパワハラを受けて裁判になり勝って損害賠償などを受けた。そうしたらパワハラをした側で家庭崩壊してしまったのだそうです。そういうこともあるのだという自覚が必要です。
徳永各々の正義の中で差別は生まれてくるわけだから、それに対抗するためにアートの力は必要なのだと思います。
明利普段体験できない物語、色んな次元の物語を見せてあげるのも演劇の役割だと思います。争いになったとき、相手を理解してあげられる東京であって欲しいです。
──ではそろそろ、上原さんの挙げてくれた「空気」について話しましょう。
上原私は見ている間ずっと息ができない感じでした。まるで空気が悪い状態の中にいるようで。それで「空気」を挙げたんです。

上原諒子さん
上原「息を吐ける場所」を作ることも大事ですよね。否定せずにいること、「刷り込み」をしないこと…そういうことの積み重ねで「空気」は出来上がっていくのでは?
──明らかなのは、マイノリティの人々が安心して息を吐ける場所にしないといけないということです。「息を吐く」でいうと「身体」というのも大事なキーワードであり、演劇の武器だよね。
崔もしコロナ禍がなくて、この舞台を生で観て俳優の身体を直接感じることができたらどうだったのだろう? 僕は最近「human connection」という言葉について考えます。コロナ禍で私たちも色々なことを考え、演劇の方向性も変わっていくでしょう。
李観客も考えないといけないところが演劇の素晴らしいところです。でも、一人で観に行ってもこうやって話し合って考えを吐き出すことはできないわけで、今日のようなチャンスはありがたいです。みなさんに「ありがとう!」と言いたいです。
──チリの現代劇が私たちの住む東京とそのままつながっている。また、李君の言うように、芸術祭という場で、このようなセッションの場が設けられたこと、さらには、ここで話されたことが公開される段取りになっている。コロナ禍の中で催された特殊な上演だったけれど、今回は、受け取る側の、つまり、観客のあり方を問う、芸術祭であったようにも思われます。
文:中本千晶(ライター)