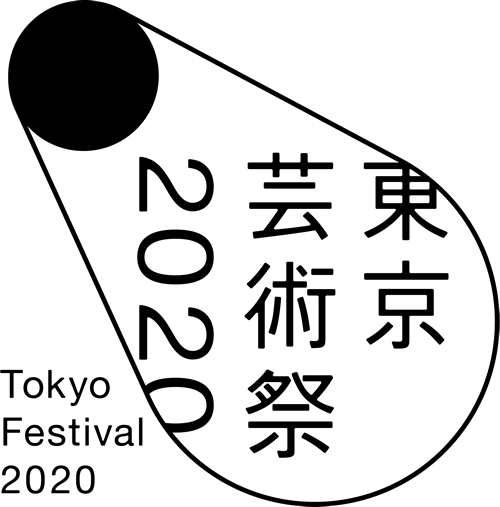『フィガロの結婚』観劇レポート
それ以来のオペラ鑑賞、また私はやらかしてしまうのではないか?そんな不安感を覚えつつも、野田秀樹に根っからミーハーな私にとって「モーツァルト/歌劇『フィガロの結婚』~庭師は見た!~(再演)」を観ないという選択肢はなかった。
しかしこの不安感は開演5分後にはすっかり雲散霧消していた。オペラに対する、言葉を選ばなければ「おしとやかすぎる」「お上品すぎる」「刺激が少ない」という印象を、予想を遥かに上回るパワーで破壊してくれた。
「静」と「動」。野田作品はこれらのバランスの最適解をもってして観客に心地良い刺激をもたらしていると感じる。ストーリーや楽曲における「原典」と「日本語による言葉あそび」、演出における「シンプルな道具」(今回で言うと何にでもなる棒)としなやかに動く「人体」…。この野田作品における絶妙な「動」の力が、私たちの心をくすぐりつづけていると確信する。
野田版『フィガロの結婚』で最たる「動」の存在は、言うまでもなく「庭師アントニ男」である。狂言回しの存在はストーリーに対して強力な推進力を持つ。小説であれば地の文で補足できることも、あからさまな狂言回しがいない演劇やオペラでは、最低限必要な説明を登場人物に語らせ/歌わせざるを得ない。この補足の厳しさによるストーリーの理解の難化、ストーリーの進みのスロー化は特にオペラで際立つ。しかし、本作ではアントニ男という、よく喋る喋りまくる狂言回しが登場することによって、オペラ独特のストーリーの理解を助け、さらにテンポを加速させることを可能にしている。
目にも耳にも心地よい断続的な驚きがもたらされる野田版『フィガロの結婚』。一度オペラを挫折したことがある人にこそ、オペラアレルギーの克服への特効薬になると確信している。
(注)遭遇すれば「よっ」と簡単な挨拶を交わすが、それ以上の付き合いがないという程度の友だち関係を示す俗語。