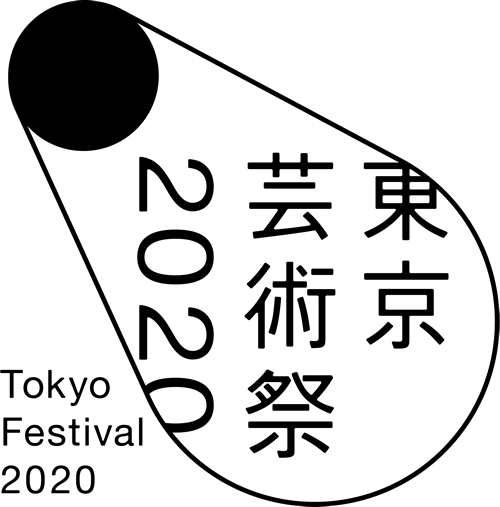『ビッグ・ナッシング』観劇レポート
この作品の地盤となっている中国の怪異記事集成『酉陽雑俎』は、人間だけではなく動物や自然、神仏などにおけるあらゆる異事が記されており、いわば、日常にある不思議、不気味さを著した作品と言える。あの影絵における反復的な動きや、人間と動植物の交わったグロテスクな黒い影は、一つとして言葉はなく、時として音もなく、ただ動いて、変化し、消滅、収去されるばかりである。この一連の流れは見る者に、ただひたすら得体の知れない狂気を与える。この狂気とは、目の前で起こっていることが一切として説明されず、意味さえも解明されず、ただ見せられているという不可解さがもたらす狂気である。それは、前述したように、影絵が仕掛ける単調でモノクロームな世界がより一層この不可解な状況を増幅させ、『酉陽雑俎』で著される意味の持ち得ない日常の断片を、文字通りタイトルの『ビッグ・ナッシング』に回帰されるテーマに導いているように感じた。
翻って考えてみると、気が遠くなるほどの不可解な世界に意味を求めようとしているのは人間だけであって、この広すぎる世界がもたらす人間の理知を超える出来事の下で、人間は生きているのではないだろうか。それを感じたのは、影絵の中の不可解な世界に突然、作・演出、そして出演している戴陳連が入っていった瞬間である。われわれ人間が、わからなければならないと捉えているこの世界で、捉え得ていることなどこの影絵の中の世界に入り込んで感じる暗さほど不明瞭で、一方で確実に輪郭を感じてしまうほどの不気味なものばかりなのではないだろうか。しかしながら、この作品にある種の懐かしさを感じたのは、あの不気味な世界はもしかすると私たちがもっと子供の頃に見ていた世界の姿なのかもしれない。世界をもっと直感で捉えていた頃を、私はなぜか思い出した。