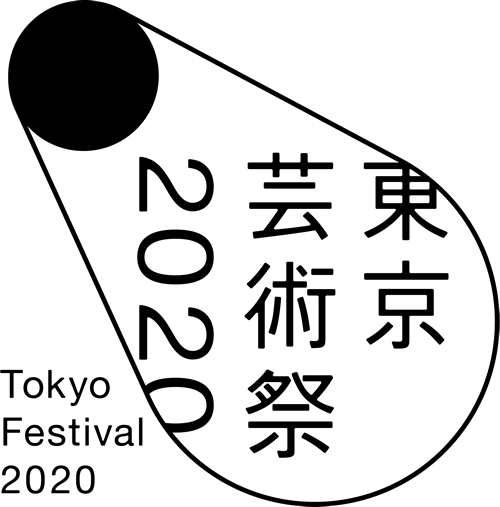『汝、愛せよ』観劇レポート
キャラクターとして特に記憶に残ったのはフェルナンドとアウトゥーロの二人だ。
フェルナンドは過去に自身が従弟に差別を行った過去を持ち、差別が生物学や性別などから来るものではなく「よくわからないまま」周囲の発言や先入観によって差別的な考えを植え付けられている事を身をもって体験しながらも、アメナイトに対して恐怖を抱いている一人だ。コンベンション前日に彼の体験や考え方を聞いた同僚のベロニカは彼を非難し考えを改める事を促すが、アウトゥーロだけは「彼に感情を無理強いは出来ない」と彼を擁護する姿を見せた。それはアウトゥーロ本人が本能的な拒絶感を自身の中に秘めていたからだとその後わかるのだが、フェルナンドはその時「自分の感情を否定しない存在」にひどく安堵した表情を見せたのが印象的だった。
フェルナンドのように「差別をしてはいけないという考えはあるが、未知なる相手への恐怖がぬぐえない」という人は現代にも多く存在し、今日までに存在する多くの漠然とした偏見意識に繋がっているのかもしれないと私は思った。
もう一人のアウトゥーロは前述したようにフェルナンドを擁護する発言をしたものの、物語の終盤で彼は性的倒錯者やアメナイトを本能的に拒絶してしまっている人間であることが発覚し、追放される形になってしまう。アウトゥーロのような本能的に他者(アメナイトや性的倒錯者)に対して拒否反応を示す人間も存在しているという提示は、終盤にも拘らず差別問題の複雑さを思わせるシーンとなっていた。
フェルナンドとアルトゥーロの共通点は互いに理由や理屈のない恐怖や嫌悪が自身の根底に存在しているという点であり、同時に私たちにも同じように「本能的な拒絶感」が存在している事を意識させる役割を持つキャラクターだ。彼らの存在には「個々の根底にある本能的な拒絶感に、我々はどう向き合っていくべきなのか?」を考えていく必要があるというメッセージ性を持っていると私は思った。
また、物語の中では度々「気まずさ」という言葉が挙げられ、ラストのシーンでも「気まずくなった時に(このディスカッションを)はじめよう。」という言葉で終わっており、差別と同様に重要なキーワードとなる言葉であると感じた。
私は劇中で言われている「気まずさ」というのは、自分の居心地の悪さ(緊張したくないという思い)や自身の考え方に対する後ろめたさを表しているように思った。「気まずさ」は「悪」であり、無くしてしまいたいと思う。そして自身の後ろめたさを解消したい為に自己満足的に他者に対して「対等な関係」を強要しようとするが、結局新たな追放や険悪さを生んでしまう事を冒頭のシーンやそれぞれのキャラクターの秘められていた過去を通して示唆しているのではないかと推測する。
ディスカッション当日のシーンで「問題視しなければならないのは「彼ら(アメナイト)が絶対的に善良である」という我々の決めつけがその人から人間性を奪う事になる事である」というような内容を見た時に非常に感心した。だが、全てを見終えてみると私には「お互いを対等に見つめ合い差別を克服しよう」という考えこそが都合の良い決めつけであり押し付けなのではないかという疑問を覚えた。
何故なら、あれほどまでに尊厳や差別の克服を強く訴えてきたベロニカが実はアメナイトに刃物で刺されていたというシーンがあったからだ。ベロニカを刺したアメナイトが「私たちを敵だと言え」と言ったように、差別されているからこそ成り立つ憎悪が彼らを生かすエネルギーになっているのだとしたら?アメナイト達個人個人の本来の考えやエネルギーを深く理解する事もなく、自分の慢心を問いただすこともなく、ただ平等を訴えているだけの我々がどれほど無知で野蛮な存在であるのかを思い知らされるような気持ちになった。物語の最後にベロニカがあのグロテスクな傷を暴露する事で、改めて自己満足と恐怖の払拭のために他者と対等であることを望む事のおこがましさを突き付けられたのだ。
つまり、我々が考えなければいけないのは「差別をなくして平等にすること」ではなく、「誰の為の差別で、誰の為の平等を叫んでいるのか?」という点であり、自分達が訴えている平等が自分達の「気まずさ」を解消したいが為の自己満足になっていないかを今一度思い直す必要があるという事なのだと私は考える。