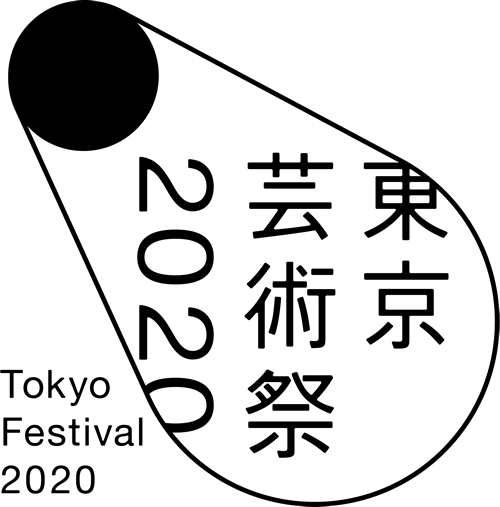『汝、愛せよ』観劇レポート
さて、その「気まずくなりたくない」という言葉、もしくはテーマが、冒頭に設けられた古典(シェイクスピア?)的な風貌、内容のショートストーリーによって示され、物語は始まる。ここでショートストーリーと言い表してしまったのは、その古典劇的ワンシーンがのちの物語に全く絡まなかったからだ。あれは何だったのだろうか...。昔話の普遍性、教育性を逆手にとった手法だろうか。今も昔も変わりませんよ、と。いずれにせよ、メッセージはその前後の時代設定とヴィジュアルの落差から鮮明に脳裏に焼き付いた。結果としては効果的だったと思う。
「差別」というものを考えるとなると、私たちはよく大きく物事を捉えてしまって、小さな差別を、というか「人間一人とて同じ奴はいない」という当たり前のことを、見落としてしまう。倫理や物事の道理を唱えるのに夢中になってしまって、何気ない言動で誰かを傷つけてしまっているかもしれないという「危険性」を忘れてしまう。その現状が作品の中であらわにされていた。特にあの場面だ、『ウサギそっくり』。アルトゥーロがアメナイトの運転手を殺した理由を、「弟のため」「差別主義だから」によるものだと思って観ていたら、『ウサギそっくり』でゾッとしたという人は多くいるのではなかろうか。あの時の気まずさったら、ない。
差別というが、要は言葉のナイフで。それが大なり小なり常に飛び交う空間で、観ていて冷やりとする場面もいくつかあった。小さなナイフで何気なく傷つけられた人は、大体の理由が個人的な感覚によるところが大きく、それは解決するには「傷ついた、謝って欲しい」と伝えるしかない。しかし、それほど言葉にしづらいこともない。だから、大体は本人の中に押し込められ、そしていつしか爆発して表面化する。そこで初めて傷つけた側も気付く。しかし、時すでに遅し、宙ぶらりんな空気が生まれてしまう。どこにもいけない、宙ぶらりんな空気。これは大きなナイフでも起こりうる。いまだ解決されていない根深い問題というのはどこの国にもあるはずで、そこにナイフが突き刺さると、見事に皆宙ぶらりんになってしまう。そんな宙ぶらりんの連続で、最後まで問題提起を突きつけられた。「プレゼンを作成したから」と「アメナイト殺しだから追放」の間で宙ぶらりんになるアルトゥーロの姿は見ていて実に心苦しかった。
移民というものに長い歴史のあるチリならではの作品だったが、在日外国人が増え、問題視され未だ解決されていない日本も他人事ではないと感じた。小さなナイフに関しては万国共通の問題だ。そうして、そこでタイトルの「愛せよ」という言葉に目が止まる。自分以外の存在をどれだけ愛せるか、つまりは信じられるか、ということか。しかし、その中で繰り返される「気まずくなりたくない」という言葉は、皮肉にも差別に立ち向かう我々のどこかに抱える本音にも思えてしまう。