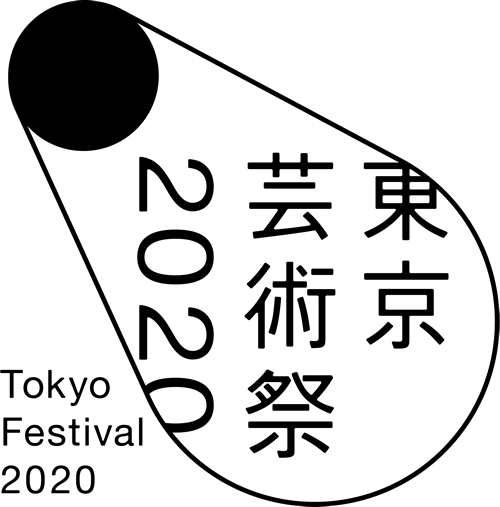『ビッグ・ナッシング』観劇レポート
その抽象的なものの中で言葉というものが発せられない。それにより、我々劇場に集う人間たちが何を描かれているかを必死に模索していた。今このコロナ禍で劇場に人が集まらず、劇場というものの古き良き形が失われつつあるものが、この劇により少しよみがえったような気がする。この劇はきっと何か固有名詞を置いての作品ではない気がする。
もちろん戴陳連の中には何かしらの伝えたいこと、形があると思う。だがそれを我々には非常にわかりずらく、なんなら答えを導かないようにさせている気がする。それはきっと我々観客という人類に考えて答えにたどり着いてほしいというものなのか、それとも我々が考えたもの1つ1つが答えであり、正解などないのか。そこのはっきりした部分はわからない。
この作品は影絵で我々観客に「何か」を伝えようとしてきている。課題を出されている3つの中でセリフがない演劇はこれだけだった。というよりか、今この現代にセリフのない演劇は中々に珍しい。多くの小劇場、大劇場で上演されているものは我々にとても分かりやすく伝えられ、ちゃんと理解されるために多くの情報を伝えてくれるものがほとんどだ。
だがこの劇は影絵、照明、音響、そしてこの劇の一番重要な部分ともいえる戴陳連の熱量のみで語られる。この戴陳連の熱量が一番重要だと思う。この作品にかけている思いなどがそこには表れている。そしてその熱量で私たち観客はこの劇を見ていられるのかもしれない。
だが2.3回ほど、この作品の中で戴陳連が小さな照明の中でただ佇む瞬間があった。
もちろんそのシーンの意味、解釈は人それぞれだが、私はそのシーンを見てなんだか‘‘ホッ‘‘とした。それはあのシーンがあるまでは戴陳連が演出家という人間ではなく、あの作品に登場する幻影に見えたからだ。途中「これは一体だれが作っているんだろう」と感じることがあった。彼が作品の中に溶け込みすぎており、1つの登場人物になってしまっていたのだ。
すなわち、彼も「影絵の影」になっていたとでもいうべきだろうか。あの佇む瞬間こそが私たち観客にとっても、彼にとっても作品の中で人間に戻れた瞬間なのだと私は思う。
総じて、この劇は本当に難しかった。だからこそもう1度見たい。もう1度見て、僕たちが持っている想像力をフルに使いたい。
この「想像の暴力」ともいえる作品は、このコロナ禍だからこそ見るべきなのではないかと感じた。